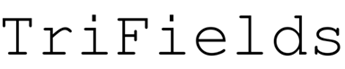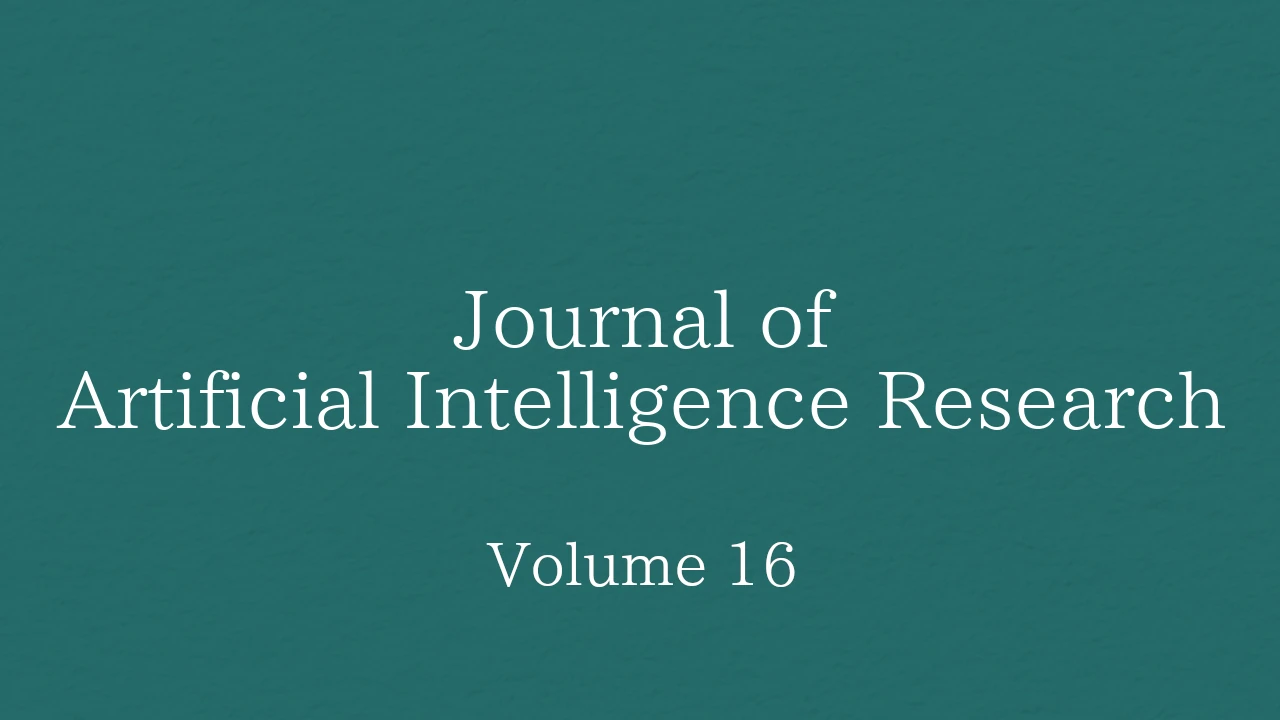Journal of Artificial Intelligence Resarch Vol. 16 (2002)に記載されている内容を一覧にまとめ、機械翻訳を交えて日本語化し掲載します。
Accelerating Reinforcement Learning by Composing Solutions of Automatically Identified Subtasks
自動識別されたサブタスクの解を合成することによる強化学習の高速化
This paper discusses a system that accelerates reinforcement learning by using transfer from related tasks. Without such transfer, even if two tasks are very similar at some abstract level, an extensive re-learning effort is required. The system achieves much of its power by transferring parts of previously learned solutions rather than a single complete solution. The system exploits strong features in the multi-dimensional function produced by reinforcement learning in solving a particular task. These features are stable and easy to recognize early in the learning process. They generate a partitioning of the state space and thus the function. The partition is represented as a graph. This is used to index and compose functions stored in a case base to form a close approximation to the solution of the new task. Experiments demonstrate that function composition often produces more than an order of magnitude increase in learning rate compared to a basic reinforcement learning algorithm.
本論文では、関連タスクからの転移を用いて強化学習を加速するシステムについて論じる。このような転移がなければ、2つのタスクが抽象レベルで非常に類似している場合でも、大規模な再学習が必要となります。このシステムは、単一の完全な解ではなく、以前に学習した解の一部を転移することで、その威力を発揮します。このシステムは、特定のタスクを解決する際に、強化学習によって生成される多次元関数の強力な特徴を活用します。これらの特徴は安定しており、学習プロセスの初期段階で容易に認識できます。これらの特徴は状態空間の分割、ひいては関数を生成します。パーティションはグラフとして表現されます。これは、ケースベースに格納された関数をインデックス化して合成し、新しいタスクの解に近い近似値を形成するために使用されます。実験では、関数合成は、基本的な強化学習アルゴリズムと比較して、学習率を1桁以上向上させることがしばしば実証されています。
Extensions of Simple Conceptual Graphs: the Complexity of Rules and Constraints
単純な概念グラフの拡張:ルールと制約の複雑さ
Simple conceptual graphs are considered as the kernel of most knowledge representation formalisms built upon Sowa’s model. Reasoning in this model can be expressed by a graph homomorphism called projection, whose semantics is usually given in terms of positive, conjunctive, existential FOL. We present here a family of extensions of this model, based on rules and constraints, keeping graph homomorphism as the basic operation. We focus on the formal definitions of the different models obtained, including their operational semantics and relationships with FOL, and we analyze the decidability and complexity of the associated problems (consistency and deduction). As soon as rules are involved in reasonings, these problems are not decidable, but we exhibit a condition under which they fall in the polynomial hierarchy. These results extend and complete the ones already published by the authors. Moreover we systematically study the complexity of some particular cases obtained by restricting the form of constraints and/or rules.
単純な概念グラフは、Sowaモデルに基づくほとんどの知識表現形式主義の中核と考えられています。このモデルにおける推論は、射影と呼ばれるグラフ準同型によって表現することができ、その意味は通常、肯定的、連言的、存在的FOLによって与えられます。本稿では、グラフ準同型を基本操作として、ルールと制約に基づくこのモデルの拡張ファミリーを提示します。得られた様々なモデルの形式的定義、特に操作的意味論やFOLとの関係に焦点を当て、関連する問題(一貫性と演繹)の決定可能性と複雑性を分析します。推論にルールが関与すると、これらの問題は決定不可能となるが、多項式階層に該当する条件を示す。これらの結果は、著者らが既に発表した結果を拡張し、補完するものです。さらに、制約やルールの形式を制限することで得られる特定のケースの複雑性を体系的に検討します。
The Communicative Multiagent Team Decision Problem: Analyzing Teamwork Theories and Models
コミュニケーション型マルチエージェントチーム意思決定問題:チームワーク理論とモデルの分析
Despite the significant progress in multiagent teamwork, existing research does not address the optimality of its prescriptions nor the complexity of the teamwork problem. Without a characterization of the optimality-complexity tradeoffs, it is impossible to determine whether the assumptions and approximations made by a particular theory gain enough efficiency to justify the losses in overall performance. To provide a tool for use by multiagent researchers in evaluating this tradeoff, we present a unified framework, the COMmunicative Multiagent Team Decision Problem (COM-MTDP). The COM-MTDP model combines and extends existing multiagent theories, such as decentralized partially observable Markov decision processes and economic team theory. In addition to their generality of representation, COM-MTDPs also support the analysis of both the optimality of team performance and the computational complexity of the agents’ decision problem. In analyzing complexity, we present a breakdown of the computational complexity of constructing optimal teams under various classes of problem domains, along the dimensions of observability and communication cost. In analyzing optimality, we exploit the COM-MTDP’s ability to encode existing teamwork theories and models to encode two instantiations of joint intentions theory taken from the literature. Furthermore, the COM-MTDP model provides a basis for the development of novel team coordination algorithms. We derive a domain-independent criterion for optimal communication and provide a comparative analysis of the two joint intentions instantiations with respect to this optimal policy. We have implemented a reusable, domain-independent software package based on COM-MTDPs to analyze teamwork coordination strategies, and we demonstrate its use by encoding and evaluating the two joint intentions strategies within an example domain.
マルチエージェントチームワークは大きく進歩しているにもかかわらず、既存の研究では、その処方箋の最適性やチームワーク問題の複雑性は取り上げられていない。最適性と複雑性のトレードオフを特徴づけなければ、特定の理論における仮定や近似が、全体的なパフォーマンスの損失を正当化するのに十分な効率性を獲得しているかどうかを判断することは不可能です。マルチエージェント研究者がこのトレードオフを評価するためのツールを提供するために、我々は統一的な枠組みである通信型マルチエージェントチーム決定問題(COM-MTDP)を提示します。COM-MTDPモデルは、分散型部分観測マルコフ決定過程や経済的チーム理論といった既存のマルチエージェント理論を統合・拡張します。COM-MTDPは、その表現の汎用性に加えて、チームパフォーマンスの最適性とエージェントの意思決定問題の計算複雑性の両方の分析をサポートします。複雑性の分析においては、様々な問題領域における最適チーム構築の計算複雑性を、観測可能性と通信コストの観点から分類します。最適性の分析において、我々は既存のチームワーク理論とモデルを符号化するCOM-MTDPの能力を活用し、文献から得られた共同意図理論の2つの具体例を符号化します。さらに、COM-MTDPモデルは、新しいチームコーディネーションアルゴリズム開発の基盤を提供します。我々は、最適なコミュニケーションのためのドメイン非依存の基準を導出し、この最適ポリシーに関して2つの共同意図の具体例を比較分析します。我々は、チームワークコーディネーション戦略を分析するために、COM-MTDPに基づく再利用可能でドメイン非依存のソフトウェアパッケージを実装し、例となるドメイン内で2つの共同意図戦略を符号化および評価することにより、その使用法を実証します。
Collective Intelligence, Data Routing and Braess’ Paradox
集合知、データルーティング、そしてブライスのパラドックス
We consider the problem of designing the the utility functions of the utility-maximizing agents in a multi-agent system so that they work synergistically to maximize a global utility. The particular problem domain we explore is the control of network routing by placing agents on all the routers in the network. Conventional approaches to this task have the agents all use the Ideal Shortest Path routing Algorithm (ISPA). We demonstrate that in many cases, due to the side-effects of one agent’s actions on another agent’s performance, having agents use ISPA’s is suboptimal as far as global aggregate cost is concerned, even when they are only used to route infinitesimally small amounts of traffic. The utility functions of the individual agents are not “aligned” with the global utility, intuitively speaking. As a particular example of this we present an instance of Braess’ paradox in which adding new links to a network whose agents all use the ISPA results in a decrease in overall throughput. We also demonstrate that load-balancing, in which the agents’ decisions are collectively made to optimize the global cost incurred by all traffic currently being routed, is suboptimal as far as global cost averaged across time is concerned. This is also due to `side-effects’, in this case of current routing decision on future traffic. The mathematics of Collective Intelligence (COIN) is concerned precisely with the issue of avoiding such deleterious side-effects in multi-agent systems, both over time and space. We present key concepts from that mathematics and use them to derive an algorithm whose ideal version should have better performance than that of having all agents use the ISPA, even in the infinitesimal limit. We present experiments verifying this, and also showing that a machine-learning-based version of this COIN algorithm in which costs are only imprecisely estimated via empirical means (a version potentially applicable in the real world) also outperforms the ISPA, despite having access to less information than does the ISPA. In particular, this COIN algorithm almost always avoids Braess’ paradox.
マルチエージェントシステムにおける効用最大化エージェントの効用関数を設計し、それらが相乗的に動作して全体的な効用を最大化する問題を考察します。ここで検討する具体的な問題領域は、ネットワーク内のすべてのルーターにエージェントを配置することによるネットワークルーティングの制御です。このタスクに対する従来のアプローチでは、すべてのエージェントが理想最短経路ルーティングアルゴリズム(ISPA)を使用します。多くの場合、あるエージェントの行動が別のエージェントのパフォーマンスに及ぼす副作用により、たとえ極微量のトラフィックをルーティングするためにのみISPAが使用される場合でも、エージェントにISPAを使用させることは、全体的な総コストに関する限り、最適ではないことを示します。個々のエージェントの効用関数は、直感的に言えば、全体的効用と「整合」していません。その具体的な例として、ブライスのパラドックスの事例を示します。これは、すべてのエージェントがISPAを使用するネットワークに新しいリンクを追加すると、全体のスループットが低下するというものです。また、現在ルーティングされているすべてのトラフィックにかかる全体的コストを最適化するためにエージェントの意思決定が集合的に行われる負荷分散は、時間平均の全体的コストに関して言えば、最適ではないことを示します。これはまた、「副作用」、つまり現在のルーティング決定が将来のトラフィックに及ぼす影響にも起因します。集合知(COIN)の数学は、まさにマルチエージェントシステムにおいて、時間と空間の両方において、このような有害な副作用を回避するという問題に取り組んでいます。私たちは、この数学の主要概念を提示し、それらを用いて、すべてのエージェントがISPAを使用する場合よりも、たとえ微小な極限においても優れた性能を発揮する理想的なアルゴリズムを導出します。本稿では、このことを検証する実験結果を提示します。また、コストを経験的手法によって不正確に推定するCOINアルゴリズムの機械学習版(実世界に適用可能なバージョン)も、ISPAよりも情報量が少ないにもかかわらず、ISPAを上回る性能を示す。特に、このCOINアルゴリズムはBraessのパラドックスをほぼ常に回避します。
SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique
SMOTE:合成少数派オーバーサンプリング法
An approach to the construction of classifiers from imbalanced datasets is described. A dataset is imbalanced if the classification categories are not approximately equally represented. Often real-world data sets are predominately composed of “normal” examples with only a small percentage of “abnormal” or “interesting” examples. It is also the case that the cost of misclassifying an abnormal (interesting) example as a normal example is often much higher than the cost of the reverse error. Under-sampling of the majority (normal) class has been proposed as a good means of increasing the sensitivity of a classifier to the minority class. This paper shows that a combination of our method of over-sampling the minority (abnormal) class and under-sampling the majority (normal) class can achieve better classifier performance (in ROC space) than only under-sampling the majority class. This paper also shows that a combination of our method of over-sampling the minority class and under-sampling the majority class can achieve better classifier performance (in ROC space) than varying the loss ratios in Ripper or class priors in Naive Bayes. Our method of over-sampling the minority class involves creating synthetic minority class examples. Experiments are performed using C4.5, Ripper and a Naive Bayes classifier. The method is evaluated using the area under the Receiver Operating Characteristic curve (AUC) and the ROC convex hull strategy.
不均衡なデータセットから分類器を構築するアプローチについて説明します。分類カテゴリがほぼ均等に表現されていない場合、データセットは不均衡です。現実世界のデータセットは、多くの場合、大部分が「正常」な例で構成され、「異常」または「興味深い」例はごくわずかです。また、異常(興味深い)例を正常例として誤分類するコストは、逆の誤りのコストよりもはるかに高い場合も少なくありません。分類器の少数クラスに対する感度を高めるための優れた方法として、多数(正常)クラスのアンダーサンプリングが提案されています。本論文では、少数(異常)クラスのオーバーサンプリングと多数(正常)クラスのアンダーサンプリングを組み合わせることで、多数クラスのみをアンダーサンプリングする場合よりも(ROC空間において)分類器の性能が向上することを示しています。さらに、本論文では、少数クラスをオーバーサンプリングと多数クラスをアンダーサンプリングする組み合わせにより、Ripperの損失率やNaive Bayesのクラス事前分布を変化させるよりも(ROC空間において)分類器の性能が向上することを示しています。少数派クラスをオーバーサンプリングする手法では、合成少数派クラスのサンプルを作成します。実験は、C4.5、Ripper、および単純ベイズ分類器を用いて行います。この手法は、受信者動作特性曲線(AUC)の下の領域とROC凸包戦略を用いて評価します。
Automatically Training a Problematic Dialogue Predictor for a Spoken Dialogue System
音声対話システムのための問題のある対話予測器の自動学習
Spoken dialogue systems promise efficient and natural access to a large variety of information sources and services from any phone. However, current spoken dialogue systems are deficient in their strategies for preventing, identifying and repairing problems that arise in the conversation. This paper reports results on automatically training a Problematic Dialogue Predictor to predict problematic human-computer dialogues using a corpus of 4692 dialogues collected with the ‘How May I Help You’ (SM) spoken dialogue system. The Problematic Dialogue Predictor can be immediately applied to the system’s decision of whether to transfer the call to a human customer care agent, or be used as a cue to the system’s dialogue manager to modify its behavior to repair problems, and even perhaps, to prevent them. We show that a Problematic Dialogue Predictor using automatically-obtainable features from the first two exchanges in the dialogue can predict problematic dialogues 13.2% more accurately than the baseline.
音声対話システムは、あらゆる電話から多種多様な情報源やサービスに効率的かつ自然にアクセスできることを約束します。しかしながら、現在の音声対話システムには、会話中に発生する問題を防止、特定、修復するための戦略が不十分です。本論文では、「How May I Help You」(SM)音声対話システムで収集された4692の対話コーパスを用いて、問題のある人間とコンピュータ間の対話を予測する問題のある対話予測器の自動学習結果を報告します。問題のある対話予測器は、通話を人間のカスタマーケアエージェントに転送するかどうかのシステムの判断に即座に適用できるだけでなく、システムの対話マネージャが問題を修復し、場合によっては問題を予防するために動作を変更するための手がかりとしても使用できます。対話の最初の2つのやり取りから自動的に取得される特徴量を用いた問題のある対話予測器は、ベースラインよりも13.2%高い精度で問題のある対話を予測できることを示す。
Efficient Reinforcement Learning Using Recursive Least-Squares Methods
再帰最小二乗法を用いた効率的な強化学習
The recursive least-squares (RLS) algorithm is one of the most well-known algorithms used in adaptive filtering, system identification and adaptive control. Its popularity is mainly due to its fast convergence speed, which is considered to be optimal in practice. In this paper, RLS methods are used to solve reinforcement learning problems, where two new reinforcement learning algorithms using linear value function approximators are proposed and analyzed. The two algorithms are called RLS-TD(lambda) and Fast-AHC (Fast Adaptive Heuristic Critic), respectively. RLS-TD(lambda) can be viewed as the extension of RLS-TD(0) from lambda=0 to general lambda within interval [0,1], so it is a multi-step temporal-difference (TD) learning algorithm using RLS methods. The convergence with probability one and the limit of convergence of RLS-TD(lambda) are proved for ergodic Markov chains. Compared to the existing LS-TD(lambda) algorithm, RLS-TD(lambda) has advantages in computation and is more suitable for online learning. The effectiveness of RLS-TD(lambda) is analyzed and verified by learning prediction experiments of Markov chains with a wide range of parameter settings. The Fast-AHC algorithm is derived by applying the proposed RLS-TD(lambda) algorithm in the critic network of the adaptive heuristic critic method. Unlike conventional AHC algorithm, Fast-AHC makes use of RLS methods to improve the learning-prediction efficiency in the critic. Learning control experiments of the cart-pole balancing and the acrobot swing-up problems are conducted to compare the data efficiency of Fast-AHC with conventional AHC. From the experimental results, it is shown that the data efficiency of learning control can also be improved by using RLS methods in the learning-prediction process of the critic. The performance of Fast-AHC is also compared with that of the AHC method using LS-TD(lambda). Furthermore, it is demonstrated in the experiments that different initial values of the variance matrix in RLS-TD(lambda) are required to get better performance not only in learning prediction but also in learning control. The experimental results are analyzed based on the existing theoretical work on the transient phase of forgetting factor RLS methods.
再帰最小二乗法(RLS)アルゴリズムは、適応フィルタリング、システム同定、適応制御において最もよく知られているアルゴリズムの1つです。その人気の理由は主に収束速度が速いことであり、これは実用上最適であると考えられています。本稿では、強化学習問題を解くためにRLS法を用い、線形価値関数近似器を用いた2つの新しい強化学習アルゴリズムを提案し、解析します。2つのアルゴリズムはそれぞれRLS-TD(lambda)とFast-AHC(Fast Adaptive Heuristic Critic)と呼ばれます。RLS-TD(lambda)は、RLS-TD(0)をλ=0から区間[0,1]内の一般λまで拡張したものとみなすことができるため、RLS法を用いた多段階の時間差分(TD)学習アルゴリズムとなります。RLS-TD(lambda)はエルゴードマルコフ連鎖に対して確率1での収束と収束限界が証明されています。既存のLS-TD(lambda)アルゴリズムと比較して、RLS-TD(lambda)は計算上の利点があり、オンライン学習により適しています。RLS-TD(lambda)の有効性は、幅広いパラメータ設定によるマルコフ連鎖の学習予測実験によって分析・検証されています。Fast-AHCアルゴリズムは、提案されたRLS-TD(lambda)アルゴリズムを適応型ヒューリスティック批評法の批評ネットワークに適用することによって導出されます。従来のAHCアルゴリズムとは異なり、Fast-AHCはRLS法を利用して批評における学習予測効率を向上させる。カートポールバランシング問題とアクロボット振り上げ問題の学習制御実験を実施し、Fast-AHCと従来のAHCのデータ効率を比較した。実験結果から、批評の学習予測プロセスでRLS法を用いることで、学習制御のデータ効率も向上できることが示されました。Fast-AHCの性能は、LS-TD(λ)を用いたAHC法の性能とも比較されます。さらに、実験では、RLS-TD(λ)における分散行列の初期値を変えることで、学習予測だけでなく学習制御においても性能向上が期待できることが示されました。実験結果は、忘却係数RLS法の過渡期に関する既存の理論的研究に基づいて分析されています。
Structured Knowledge Representation for Image Retrieval
画像検索のための構造化知識表現
We propose a structured approach to the problem of retrieval of images by content and present a description logic that has been devised for the semantic indexing and retrieval of images containing complex objects. As other approaches do, we start from low-level features extracted with image analysis to detect and characterize regions in an image. However, in contrast with feature-based approaches, we provide a syntax to describe segmented regions as basic objects and complex objects as compositions of basic ones. Then we introduce a companion extensional semantics for defining reasoning services, such as retrieval, classification, and subsumption. These services can be used for both exact and approximate matching, using similarity measures. Using our logical approach as a formal specification, we implemented a complete client-server image retrieval system, which allows a user to pose both queries by sketch and queries by example. A set of experiments has been carried out on a testbed of images to assess the retrieval capabilities of the system in comparison with expert users ranking. Results are presented adopting a well-established measure of quality borrowed from textual information retrieval.
我々は、コンテンツによる画像検索の問題に対する構造化アプローチを提案し、複雑なオブジェクトを含む画像の意味的索引付けと検索のために考案された記述論理を提示します。他のアプローチと同様に、画像解析によって抽出された低レベルの特徴から出発し、画像内の領域を検出して特徴付ける。しかし、特徴ベースのアプローチとは対照的に、我々はセグメント化された領域を基本オブジェクトとして、そして複合オブジェクトを基本オブジェクトの組み合わせとして記述するための構文を提供します。次に、検索、分類、包含といった推論サービスを定義するための、付随的な拡張的意味論を導入します。これらのサービスは、類似度尺度を用いた完全一致と近似一致の両方に利用可能です。我々の論理的アプローチを形式仕様として用い、我々は完全なクライアントサーバー型画像検索システムを実装した。このシステムでは、ユーザーはスケッチによるクエリと例によるクエリの両方を実行できます。システムの検索能力を熟練ユーザーによるランキングと比較するために、画像テストベッド上で一連の実験を実施した。テキスト情報検索から借用した、確立された品質尺度を採用した結果が提示されています。
Learning Geometrically-Constrained Hidden Markov Models for Robot Navigation: Bridging the Topological-Geometrical Gap
ロボットナビゲーションのための幾何学的制約付き隠れマルコフモデルの学習:位相幾何学的ギャップの橋渡し
Hidden Markov models (HMMs) and partially observable Markov decision processes (POMDPs) provide useful tools for modeling dynamical systems. They are particularly useful for representing the topology of environments such as road networks and office buildings, which are typical for robot navigation and planning. The work presented here describes a formal framework for incorporating readily available odometric information and geometrical constraints into both the models and the algorithm that learns them. By taking advantage of such information, learning HMMs/POMDPs can be made to generate better solutions and require fewer iterations, while being robust in the face of data reduction. Experimental results, obtained from both simulated and real robot data, demonstrate the effectiveness of the approach.
隠れマルコフモデル(HMM)と部分観測マルコフ決定過程(POMDP)は、動的システムをモデリングするための有用なツールを提供します。これらは特に、ロボットのナビゲーションとプランニングに典型的な道路網やオフィスビルなどの環境のトポロジーを表現するのに役立ちます。本研究では、容易に利用可能なオドメトリック情報と幾何学的制約を、モデルとそれらを学習するアルゴリズムの両方に組み込むための正式なフレームワークについて説明します。このような情報を活用することで、学習HMM/POMDPは、データ削減に対して堅牢でありながら、より優れた解を生成し、反復回数を減らすことができます。シミュレーションと実際のロボットデータの両方から得られた実験結果は、このアプローチの有効性を実証しています。
Improving the Efficiency of Inductive Logic Programming Through theUse of Query Packs
クエリパックを用いた帰納的論理プログラミングの効率向上
Inductive logic programming, or relational learning, is a powerful paradigm for machine learning or data mining. However, in order for ILP to become practically useful, the efficiency of ILP systems must improve substantially. To this end, the notion of a query pack is introduced: it structures sets of similar queries. Furthermore, a mechanism is described for executing such query packs. A complexity analysis shows that considerable efficiency improvements can be achieved through the use of this query pack execution mechanism. This claim is supported by empirical results obtained by incorporating support for query pack execution in two existing learning systems.
帰納論理プログラミング(関係学習)は、機械学習やデータマイニングにおける強力なパラダイムです。しかし、帰納論理プログラミング(ILP)を実用的に有用にするためには、ILPシステムの効率を大幅に向上させる必要があります。この目的のために、類似したクエリの集合を構造化するクエリパックの概念が導入されます。さらに、このようなクエリパックを実行するためのメカニズムについて説明します。複雑性分析により、このクエリパック実行メカニズムの使用により、大幅な効率向上が達成できることが示されています。この主張は、既存の2つの学習システムにクエリパック実行のサポートを組み込むことで得られた実証結果によって裏付けられています。
Optimizing Dialogue Management with Reinforcement Learning: Experiments with the NJFun System
強化学習による対話管理の最適化:NJFunシステムを用いた実験
Designing the dialogue policy of a spoken dialogue system involves many nontrivial choices. This paper presents a reinforcement learning approach for automatically optimizing a dialogue policy, which addresses the technical challenges in applying reinforcement learning to a working dialogue system with human users. We report on the design, construction and empirical evaluation of NJFun, an experimental spoken dialogue system that provides users with access to information about fun things to do in New Jersey. Our results show that by optimizing its performance via reinforcement learning, NJFun measurably improves system performance.
音声対話システムの対話ポリシーの設計には、多くの重要な選択が伴います。本論文では、対話ポリシーを自動的に最適化する強化学習アプローチを提示します。このアプローチは、人間ユーザーとの実用対話システムに強化学習を適用する際の技術的課題に対処します。ニュージャージー州の楽しいアクティビティに関する情報へのアクセスをユーザーに提供する実験的な音声対話システムであるNJFunの設計、構築、および実証的評価について報告します。結果は、強化学習によってパフォーマンスを最適化することで、NJFunがシステムパフォーマンスを測定可能に向上することを示しています。
Fusions of Description Logics and Abstract Description Systems
記述論理と抽象記述システムの融合
Fusions are a simple way of combining logics. For normal modal logics, fusions have been investigated in detail. In particular, it is known that, under certain conditions, decidability transfers from the component logics to their fusion. Though description logics are closely related to modal logics, they are not necessarily normal. In addition, ABox reasoning in description logics is not covered by the results from modal logics. In this paper, we extend the decidability transfer results from normal modal logics to a large class of description logics. To cover different description logics in a uniform way, we introduce abstract description systems, which can be seen as a common generalization of description and modal logics, and show the transfer results in this general setting.
融合は論理を組み合わせる簡単な方法です。通常の様相論理においては、融合は詳細に研究されてきた。特に、特定の条件下では、決定可能性が構成要素の論理から融合論理に転移することが知られています。記述論理は様相論理と密接に関連しているが、必ずしも通常の様相論理ではない。さらに、記述論理におけるABox推論は、様相論理の結果ではカバーされていない。本稿では、通常の様相論理における決定可能性の転移結果を、より広範な記述論理に拡張します。異なる記述論理を統一的にカバーするために、記述論理と様相論理の共通の一般化と見なせる抽象記述システムを導入し、この一般的な設定における転移結果を示す。